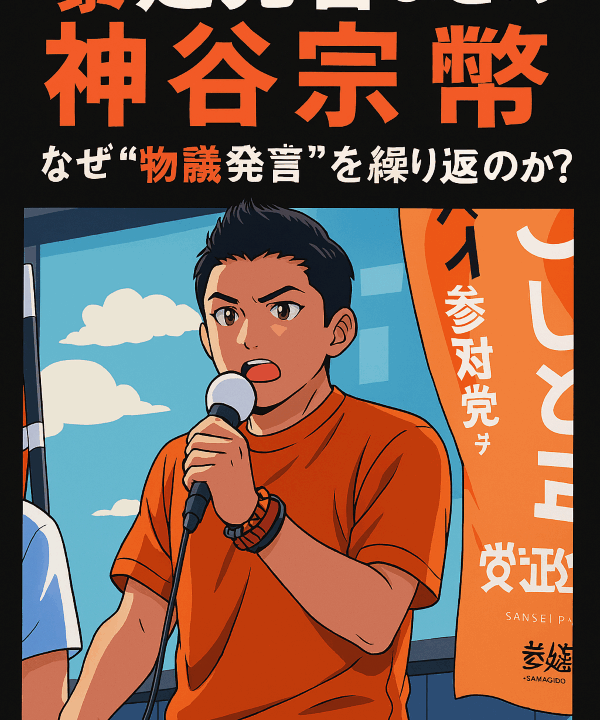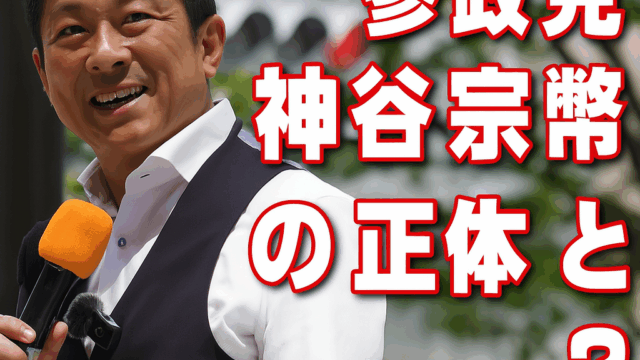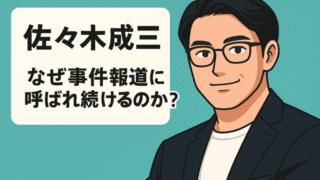〜もくじ〜
はじめに
神谷宗幣(かみやそうへい)は、2022年に政党要件を満たす勢いで急成長した参政党の代表として注目を集めています。街頭演説では多くの聴衆を集め、SNSでは熱心な支持者が拡散するなど、強烈な存在感を放っています。
しかしその一方で、彼の発言はたびたびメディアや世間を騒がせてきました。「女性蔑視では?」「歴史認識が危うい」といった批判が殺到することも多く、選挙期間中に炎上するケースも少なくありません。
これらの発言は、単なる“言い間違い”というレベルを超え、一貫した思想に基づく主張として繰り返されているのが特徴です。そのため、参政党の基本的な理念や政策の方向性とも深く結びついています。
本記事では、神谷宗幣が過去から現在に至るまでに発した「物議発言」を時系列でまとめ、それぞれの社会的背景や批判のポイントについて解説していきます。
読み進めていくことで、なぜ彼の発言が炎上を招くのか、またその裏にある思想や戦略がどのようなものかが見えてくるはずです。
プロフィール紹介
この投稿をInstagramで見る
神谷宗幣(かみやそうへい)は、1977年生まれの政治家で、現在は参政党の代表を務めています。大阪府吹田市出身で、早稲田大学政治経済学部を卒業後、福井県庁に入庁。その後、司法試験を目指すも断念し、地元・吹田市の市議会議員として政治の道を歩み始めました。
2011年には衆議院議員選挙に日本維新の会から出馬し落選。政界での本格的な活動を続ける中で、2020年に「教育・情報・食と健康・国まもり」を柱とした新党・参政党の立ち上げに関わり、2022年の参院選では比例代表で当選しました。
神谷宗幣は、政治家としては異例のほどに街頭演説を重視しており、地方都市でも数百人〜千人規模の集客を見せることも少なくありません。YouTubeチャンネルやSNSなどを駆使し、自らの言葉で訴えるスタイルを貫いています。
思想的には、伝統的な保守思想に基づきながらも、「グローバリズム批判」や「自立した国民づくり」「日本の精神性回復」などをキーワードに掲げ、教育や食の安全保障、ジェンダー政策などで独自色を打ち出しています。
その一方で、過激・極端と受け取られかねない発言も多く、たびたびネット上や報道番組で炎上の的になることも。今回紹介する“物議を醸す発言”の背景には、こうした思想的スタンスが色濃く反映されています。
問題発言①:女性の社会進出が少子化の原因?
神谷宗幣が最も多くの批判を浴びているテーマのひとつが、「女性の社会進出と少子化の関係性」に関する発言です。
この主張は2022年頃からたびたび公の場で繰り返されており、直近では2025年7月の参議院選挙に向けた街頭演説でも明確に語られました。
「女性の社会進出が進んだ結果、出産する人が減ってしまった。男女共同参画のような政策が、かえって国を弱体化させている」
このような趣旨の発言に対し、メディアや識者からはすぐさま批判の声が上がりました。「女性が働くから子どもが減る」とするこのロジックは、社会的にも生物学的にも単純化されすぎており、女性の生き方や権利を軽視していると受け止められたのです。
参政党は、一見滅茶苦茶なことを言っているように聴こえますが、重要な問題提起をしていると思います。
良い悪いは別として、少子化(晩婚・非婚)の主たる原因は女性の社会進出です。したがって、少子化対策は、理論的に、①女性の社会進出を抑制して専業主婦化を促進させるか、… https://t.co/nAPBab3gn1
— ひろゆき弁護士 (@bengoshihk) July 3, 2025
また、神谷宗幣はこの発言に続けて、「女性が家庭を守るのは本来の姿」「家庭が壊れれば国も壊れる」といった発言も行っており、ジェンダー観の古さや時代錯誤性を指摘する声も少なくありませんでした。
これに対して、本人や参政党側は「事実を冷静に述べただけ」「少子化の根本原因に踏み込んで議論する姿勢だ」と反論。支持者の一部からは「本音を言える政治家」「耳障りなことから逃げない勇気がある」と擁護の声も見られました。
たしかに、日本の少子化が進んでいる背景には、結婚年齢の上昇や出産年齢の高齢化といった問題があるのは事実です。しかし、それを「女性の社会進出のせい」と断言してしまうのはあまりにも短絡的であり、社会構造・経済・育児支援体制など複合的な要因を無視しているとの指摘も強くあります。
さらに問題視されたのが、神谷代表が「男女共同参画」という国の基本方針そのものを「国家衰退の原因だった」と断言したこと。これは政府や行政の長年の取り組みを全否定するものであり、実際に男女共同参画局を持つ内閣府や各地の自治体関係者からも批判的な意見が出ています。
なお、2025年7月現在、神谷宗幣はこのテーマに対して発言のトーンを弱める気配はなく、演説やSNS上でもたびたびこの主張を繰り返しています。
「女性が子どもを産まなくなったから国が滅びる」
この一言に代表されるように、神谷宗幣の発言には、科学的根拠よりも思想的信念が色濃く反映されていると感じる読者も多いはずです。
一部では、こうした発言が「保守的な家庭像に共感する層」には響いており、SNSや地方の街頭演説では拍手が起きることもあると報道されています。
しかし、全国的な目線で見ると、若い世代や女性層との価値観のギャップはますます拡大している印象です。
特に「働きながら子育てをする」ことが当たり前になりつつある現代において、こうした主張は時代の流れに逆行しているとも言えるでしょう。
この発言は、神谷宗幣という人物の思想の根幹を表す重要なエピソードであり、同時に参政党がどのような国の形を目指しているのかを読み取る手がかりでもあります。
問題発言②:出産の適齢期は25歳まで
2025年7月、神谷宗幣が街頭演説の中で放った一言が、大きな波紋を呼びました。
それは、「出産の適齢期は25歳まで」という発言です。
この発言が取り上げられたのは、参院選の選挙戦真っ只中。東京都内で行われた演説中に、神谷代表は「科学的に見ても、25歳までが妊娠・出産に最も適した時期」と語り、「日本が少子化に悩んでいるのは、この適齢期を逃す女性が増えているからだ」と指摘しました。
この発言は瞬く間にSNSで拡散され、「またか」「時代錯誤すぎる」と批判が殺到。「子どもを産むかどうか」「いつ産むか」は女性個人の選択であるべきという価値観と真っ向からぶつかる内容だったからです。
特に反発が大きかったのは、神谷宗幣のこの発言が「単なる統計上の話」にとどまらず、政策提案と結びついていた点です。
彼は続けて、「国家として25歳までに出産するよう促す社会制度を整えるべき」「教育・メディアでも適齢期の意識改革が必要」と語っており、実質的に早期出産を奨励・圧力をかけるような方向性を提案しているのです。
参政党公式がシレッと削除した部分
・子供産めるのも若い女性しかいないわけですよ
・男性や高齢の女性は子供産めない https://t.co/QSHv7N9pBG pic.twitter.com/zElU1b7ziz— アール_taro (@R_taro1221) July 3, 2025
これに対し、医療関係者や教育関係者からも強い反論が起きました。
現代の医学では、30代前半でも妊娠・出産は一般的であり、「25歳まででなければならない」といった強調は医学的にも不正確。
さらに、キャリア形成や経済的自立を優先せざるを得ない社会構造の中で、25歳という年齢だけを基準に出産を語るのは乱暴すぎるという指摘も多く出ています。
また、「国が若年出産を推進すること=女性の人生選択に国家が口を出すこと」という構図が、多くの女性の反感を買いました。
一方、神谷宗幣を擁護する声としては、「あくまで生物学的な事実を示しているだけ」「問題提起として必要な視点だった」といった意見も一定数あります。
実際に、妊娠リスクが上がる高齢出産や不妊の問題は社会的な課題であり、それ自体を語ることがタブーになってはならないという指摘も理解できる部分ではあります。
しかし問題なのは、神谷宗幣の言葉選びや主張の押しつけがましさにあります。
「25歳までに産めない人は国に貢献していないのか?」というような誤解を生む発言は、多様な生き方が認められる現代においては、非常にセンシティブなトピックです。
さらに、「出産適齢期」と言いながら、男性側の年齢や子育てへの責任についてはまったく言及がない点も、バランスを欠いていると指摘されました。
社会全体で少子化を解決するという視点が抜け落ち、「女性にだけ負担を求める」ように聞こえる点が、今回の炎上をより深刻にした要因といえます。
この発言が報じられた後、複数の女性団体が声明を出し、抗議デモも実施されました。
「個人の生き方を尊重しない政治家には未来は任せられない」「少子化対策を女性だけの責任にしないで」といった声が相次ぎ、参政党のジェンダー観そのものが問われる事態にまで発展しています。
神谷宗幣自身はその後も発言を撤回しておらず、むしろ「正しいことを言って叩かれるのはおかしい」と開き直るような態度を見せています。
こうした姿勢が、いっそうの批判を呼ぶ結果となっているのは言うまでもありません。
この「出産適齢期25歳発言」は、神谷宗幣という政治家が何を重視し、どういう価値観を持って政治活動をしているのかを象徴する発言のひとつです。
社会の多様性と国家の理想像の間で、いかにバランスを取るか。その難しさを浮き彫りにしたエピソードと言えるでしょう。
問題発言③:天皇に“側室制度”を導入?
2024年、神谷宗幣が自身のYouTubeチャンネルで行った発言が、新たな波紋を呼びました。
それは、「皇室に側室制度を復活させるべきではないか」という趣旨の発言です。
この動画の中で神谷宗幣は、少子化と皇室の存続問題を関連づけながら、「現在の皇室制度では男系男子による継承が困難になっている」「側室制度は歴史的に行われてきた正当な方法であり、日本の伝統を守るためには選択肢として議論すべきだ」と主張しました。
これに対し、当然ながら多くの批判が殺到します。
そもそも現在の皇室制度は、1947年の皇室典範制定以降、一夫一妻制を前提としており、戦後日本の民主主義と憲法に基づく「家族観」に大きく支えられています。
その中で「側室制度」を再導入するという発言は、多くの国民にとって時代錯誤であり、男女平等や人権の観点からも容認できないという声が相次ぎました。
また、政治家が公の場で皇室の在り方に対して具体的な制度改変を提案すること自体、「政治利用だ」「不敬だ」と感じる国民も少なくありません。
天皇制という極めてセンシティブなテーマに対し、神谷宗幣のようなストレートな言い回しは、保守層においても意見が割れる要因となりました。
えっ‼️選挙直前に削除したの⁉️
ほんといい加減な政党だな参政党。
この前ナチス動画を消したばっかりじゃないか!消すと増えるよ。
ロングバージョン貼っとくね。後半部が「天皇に側室」発言。 https://t.co/OMvsRZp3jc pic.twitter.com/c5Lv5e1S5H— くろやす (@kuroyasu17) July 2, 2025
一方で、神谷宗幣の支持層からは「真剣に皇室の未来を考えているからこその発言」「歴史と伝統に根ざした視点は貴重だ」といった擁護の声もありました。
たしかに、日本の皇室が直面する“後継者問題”は深刻であり、女性宮家創設や女系天皇の是非を巡る議論が続いているのも事実です。
ただ、神谷宗幣の発言が批判を招いたのは、単に「制度としての是非」を論じたからではなく、女性の人権や近代的価値観への配慮をまったく感じさせない発信スタイルにあるといえます。
しかも、この発言を取り上げたテレビ報道やネットメディアが「側室復活論を公言する政治家」と見出しを打ったことで、神谷宗幣のイメージはさらに硬直化。
一部では「古代回帰思想」と揶揄され、SNS上では「まるで封建時代」「女性を道具として扱っているのでは」といった投稿が飛び交いました。
加えて、神谷宗幣は同じ動画の中で「日本の精神性を取り戻すためには、家庭や家族の在り方を見直す必要がある」とも発言しており、ここにも保守的な価値観が色濃く表れています。
これまでにも「出産適齢期」「女性の社会進出批判」などの発言を繰り返してきた神谷氏にとって、この「側室制度復活論」は、それらと地続きにある思想的発露とも解釈できます。
つまり、単発の“失言”ではなく、一貫した国家観や家庭観に基づく発言であるという点が、多くの有権者にとっては重く受け止められているのです。
その後、神谷宗幣はこの発言について一切の撤回を行っていません。
むしろ、「メディアが意図的に切り取って批判している」と主張し、「本来の主張をしっかり理解してもらいたい」と反論を展開しています。
とはいえ、現代社会において「側室」という言葉自体が持つ重みや歴史的な背景を考えると、
政治家がそれを口にすることのインパクトは計り知れません。
そしてその言葉が、たとえ本人にその意図がなくても、多くの人に「女性の尊厳を軽んじている」と受け止められる危険性は常にあります。
この発言は、神谷宗幣がどれほど“日本的な価値”を重視しているかを示すと同時に、
その思想が現代の社会通念とどれほど乖離しているのかを象徴する発言とも言えるでしょう。
問題発言④:沖縄戦で日本軍は住民を守った?
2024年、神谷宗幣が街頭演説で語った「沖縄戦において、日本軍は住民を守った」という趣旨の発言が、地元沖縄県をはじめ全国的な批判を浴びました。
発言の背景となったのは、沖縄で開催された講演会でのスピーチ。
神谷宗幣は「メディアは沖縄戦について、日本軍が住民を見殺しにした、集団自決を強要したなどと一方的に報じているが、事実は異なる。多くの兵士は命をかけて住民を守った」と主張しました。
一見すると兵士個人の行動に焦点を当てたようにも聞こえますが、問題視されたのはその語り口と表現の強さ。
神谷宗幣は「日本軍が悪で米軍が正義という構図は歴史の捏造」とまで言い切り、現在の学校教育や教科書の記述が「自虐史観に満ちている」と断じました。
日本軍が沖縄の人たちを殺したわけじゃないと言ったのが参政党の神谷議員だ
歴史修正主義という言葉があるが、これは歴史の捏造と言ってもいいのではないか
軍が民間人にした事、それを象徴的に表しているのが久米島の事件だ(佐古忠彦氏)
6/21報道特集「久米島住民虐殺」 pic.twitter.com/DY38NwRKgL
— 弁護士福山和人 (@kaz_fukuyama) June 24, 2025
この発言に対し、沖縄県内の遺族会や歴史研究者たちからは「事実の歪曲だ」との強い反発が上がりました。
実際に沖縄戦では、旧日本軍が住民に対して「捕虜になるな」「アメリカ軍に投降するな」と命じ、結果として多数の集団自決が起きたという歴史的な記録が残っています。
また、米軍による上陸に伴い、日本軍は民家や住民の避難所を軍事施設として使用し、住民を巻き込む形での戦闘が多発したことも明らかになっています。
神谷宗幣のような「日本軍=住民を守った存在」とする言説は、これらの事実を軽視するものだと受け取られました。
加えて、この発言がなされた時期には、ちょうど沖縄戦から80周年という節目を迎えていたこともあり、地元メディアでは連日取り上げられる形に。
「県民の痛みを踏みにじるような言葉だ」「犠牲者を冒涜している」といったコメントが相次ぎました。
神谷宗幣はその後、「沖縄戦を一面的に描く報道や教科書への問題提起だった」「真実を隠すことこそ歴史への冒涜だ」と反論しましたが、批判の火はなかなか消えませんでした。
そもそもこの発言は、神谷宗幣が掲げる「歴史の見直し」という政治姿勢の一環です。
参政党は設立当初から、戦後教育のあり方に疑問を呈し、「戦前の日本には誇れる部分が多くあった」「自虐史観からの脱却を」といったメッセージを発信してきました。
しかし、そうした主張が「歴史修正主義」「美化」と見なされることも多く、特に沖縄戦のような痛ましい歴史においては、記憶と感情の衝突を生む原因になっています。
また、専門家からは「神谷宗幣は一部の証言や研究だけを引用し、全体像を無視している」といった指摘もありました。
歴史研究は多面的な視点が重要とされる中で、「政治的メッセージのために歴史を切り取って使っているのではないか」との批判が強まったのです。
結果として、この発言は参政党にとってプラスにはならず、沖縄選挙区での支持拡大にもつながりませんでした。
むしろ、「神谷宗幣=極端な歴史観」というイメージが一般層にも広がるきっかけとなり、以降の発言にも影響を与えるようになっていきます。
「歴史をどう語るか」は自由であるべきですが、その語り方が誰かの記憶や痛みを踏みにじるのであれば、それは再考されるべき──。
この一件は、政治家の言葉がもたらす社会的責任の重さをあらためて示すものでした。
問題発言⑤:移民排斥・外国人政策
神谷宗幣の発言でたびたび物議を醸しているテーマのひとつが、外国人政策・移民問題です。
2023年以降、神谷宗幣は街頭演説やSNSで「移民政策が社会秩序を壊す」「外国人労働者の受け入れは治安悪化の原因になる」といった趣旨の発言を繰り返してきました。
中でも特に炎上したのが、2024年に行われた都内の演説での次の発言です。
「日本人の税金で外国人を支援する制度はもう限界。なぜ真面目に働く日本人が、不法滞在者や技能実習生に振り回されなければならないのか」
外国人問題として批判的に報道しているのはメディアです。参政党が取り上げたのは「日本人ファースト」です。外国人排斥とは主張していません。勝手に外国人問題に置き換えてるのはメディアです。偏向報道はやめましょう。
#モーニングショー pic.twitter.com/thOcenjh9r— Elise Vanessa II IX (@ev0123456789) July 14, 2025
この発言に対しては、すぐに複数の人権団体や外国人支援団体が抗議声明を発表。
「差別を助長する発言だ」「外国人全体を一括りにして攻撃している」として、排外主義的な政治姿勢を強く批判しました。
また、SNS上でも「外国人=悪という構図を煽っている」「現代の政治家として許されない認識だ」といった批判が相次ぎ、一部のメディアでは「日本版トランプか?」という見出しまで登場しました。
一方で、神谷宗幣はこの批判に対して「現実を語っているだけ」「きれいごとでは社会は守れない」と応戦。
支持者からは「日本人の生活を第一に考える当たり前の政治家」「国民を守るという視点が抜けている政治家ばかりの中で貴重な存在」といった擁護も見られました。
実際、参政党の掲げる政策には「不法滞在外国人の厳格な取り締まり」「移民受け入れ数の制限」「外国人への生活保護廃止」といった移民規制を強化する方向性が明確に示されています。
ただし、問題となるのはその伝え方。
神谷宗幣の言葉は、「不法滞在者」や「犯罪者」への批判をしているように見せかけながら、文脈によっては「すべての外国人が日本社会にとってのリスクであるかのように聞こえる」ことがあります。
このグレーな発信が、外国人と共生している地域の住民や、多文化共生を掲げる自治体職員などから強い反発を招いているのです。
また、2025年の選挙戦では「外国人のせいで治安が悪くなった」「在日外国人が日本の文化を壊している」といった表現を含む支持者の演説動画が拡散され、ヘイトスピーチとの境界線も問われました。
神谷宗幣自身は「差別と区別は違う」として、自身の発言は制度的な問題を提起しているだけだと主張していますが、一部の人から差別感情を煽るような文脈で発言が流布されている現状は否定できません。
この件については、識者からも「参政党の外国人政策は現実問題を背景にしているが、発信の仕方に倫理的な問題がある」「誤解を与えない言葉選びをすべきだ」との指摘が出ています。
また、地方自治体では外国人住民との共生を進めてきた歴史があるため、こうした発言が地方行政の現場と対立する構図を生んでいる点も無視できません。
「国民を守る」というスローガンのもとに政策を語ること自体は否定されるべきではありませんが、
それが一部の人々への敵意や偏見と結びつくとき、政治の言葉は“刃”にもなり得るという現実を突きつけられる発言だったと言えるでしょう。
まとめ・今後の動向
ここまで見てきたように、神谷宗幣の発言は常に「正直すぎる」と「過激すぎる」の境界線を行き来しています。
男女共同参画、出産の適齢期、皇室制度、沖縄戦、移民政策──
いずれのテーマにおいても、神谷宗幣は伝統や家族観を重視する一貫した政治思想に基づいて語っています。
それが一部の保守層に響いているのは事実ですが、同時に時代の価値観や多様性とズレたメッセージが強く批判を集めているのもまた事実です。
神谷宗幣が注目される理由は、その言葉が“本音”であり、“熱”があるから。
しかし、政治家の言葉には常に「公共性」が求められます。
どれだけ本気で語っても、誰かの尊厳を踏みにじるような発言であれば、それは信頼ではなく炎上へと変わってしまいます。
参政党としては今後、政党要件を維持し、全国的な広がりを持つには
神谷宗幣のこうした言動が諸刃の剣になる可能性も否めません。
支持者にとっては「ブレない芯の強さ」でも、一般層には「危うい思想」に映るリスクがあるからです。
政治における「問題発言」は、単なる失言ではなく、その人物の価値観や世界観を映し出す鏡。
神谷宗幣がこれからどのような言葉を選び、どんな未来を描こうとしているのか──
私たちもその発言を、ただの話題性ではなく社会との“ズレ”を測るバロメーターとして冷静に見つめていく必要があるのではないでしょうか。